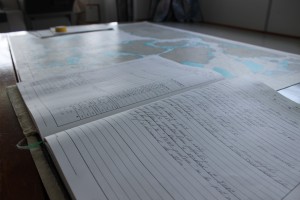弓削商船高専の練習船「弓削丸」に乗せて頂きました!
こんにちは、ふじまき@弓削です。GW、みなさまいかがお過ごしですか?
島では、「おかえり」「ひさしぶり」「大きくなったねぇ」の声があちらこちらで聞こえ、
いつもよりたいぶ人口が若返っているような気がします(笑)。
さて、弓削には国立弓削商船高専という、1901年(明治34年)に開学した歴史ある学校があります。
その歴史は、近代日本のあゆみ、旧弓削村の発展とともにありました。
日本では、鎖国が解かれ明治に入ると、台湾、中国、北米、欧州航路などの外国航路が次々と開設されました。
それに伴い、それに乗り込む船員にも、「国際的な視野と民間外交の先頭に立つ豊かな教養と行動な技術」(弓削村誌より引用)が要求されるようになりました。
そんな中、弓削島では、「船員養成機関を設けて、海外進出する以外に発展の途はない」(弓削村誌より引用)と、
海事関係者の意見が村民を動かし、知事に申請。1901年、開学を迎えることになったのです。
村民が熱望して開学した学校であるというところに、とても深い意味を感じます。
当時、村長の月俸が13円であったのに対し、校長を招請するためになんと月俸100円というお給料を提示したという記録も
残っており、村民の商船学校に対する期待のほどがうかがえます。(弓削村誌より)
そんな商船学校には、「弓削丸」という練習船があります。学生たちは、この船で航海実習に励みます。
普段、一般には公開されていないのですが、「尾道みなと祭り」で体験航海を行うということで、私も乗せて頂きました。
船全体を司る「船橋」(操縦室)にも入れて頂きました。とても緊張感ある一室でした。
目の前にひらける海原。行き交う船。安全な航海を遂行すべく、船員さんたちが厳しい目で海を見つめます。
海図やレーダー、いろんな機械がとにかくたくさんあって(しかも英語表示がほとんど)、わたしにはちんぷんかんぷん・・・
でも、なんだかカッコいいんですよね。海で働くプロフェッショナルたちの姿に、惚れ惚れしてしまいました。
こんな大きな船を動かすって、どんな気分なんだろう?
船に乗っていた学生のなかに、女の子が2名いました。商船学科の女子は学年に数人。一人だけという学年もあるのだそうです。
ふたりとも、上島町出身ではなく、寮生活を送っているそうです。
どうして商船に入ったの?と聞くと、「航海士になって、世界を見たかったから」と教えてくれました。
中学卒業の時点で「航海士になる!」と言える。こんなにも具体的な夢を持てることはすごいことなぁと思いました。
この小さな島から、ひろい世界につながっていく。それはとても誇らしいことです。